こんにちは。
保育・療育専門家のコノアス合同会社 代表 柏木です。
この記事を読んでくださる皆さんは、きっと勉強熱心な人達でしょう。
より良い支援の輪を広げていくためにも、日々、専門性をアップデートしたいものですね。
ABAと聞くと、みなさんは次のように思ってしまいませんか?
 保護者B
保護者Bよく聞く言葉だけど、ずっと難しそうってイメージがある。



専門的な指導方法なんでしょ。私にできるのかな。



研修で勉強したけど、よく分からなかったよ。
分かります。
不思議と「ABA」と聞くと、みなさん難しそうなイメージをもっているのです。
これは、非常にもったいないことです。
ということで、今回は、「ABA~応用行動分析を知ろう~」と題して、詳しくお話ししていきます。
ぜひ最後まで読んで下さいね。
ABA(応用行動分析)とは?
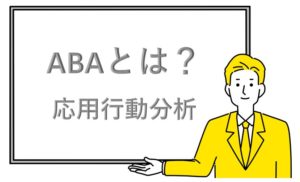
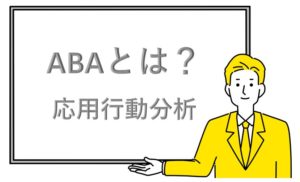
ABAとは、「Applied Behavior Analysisno」の頭文字を並べて、略称したものです。
応用行動分析学は、「人の行動は、環境との相互作用の中から生まれる。」と考えます。
つまり、「科学で人の行動を予測する学問」なのです。
応用行動分析学は、教育や療育だけでなく、動物の訓練、リハビリ、スポーツ、ビジネスなど幅広い分野で活用されています。
世界的に認められている、非常に優れた学問といえるのです。
ABA(応用行動分析学)の歴史
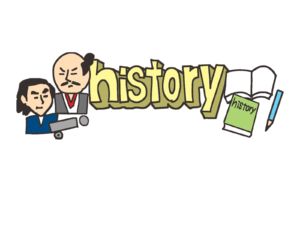
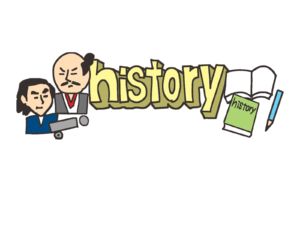
応用行動分析学は、1930年代のアメリカで生まれました。
この行動分析学は、現在の応用行動分析学の前身で、
- 人は、何故このような行動をするのか。
- 何故、その行動は続くのか。もしくは続かないのか。
- 同様の刺激を与えているのに、何故、各個人で行動が分かれるのか?
上記のような行動の「何故」を科学的に解明していったのです。
そして、研究が進むにつれ、様々な分野に行動分析学は広く適用されるようになり、学問として確立していったのです。
教育と療育~自閉症支援における有効性~


ABAは「何故その行動を取るのか。」に焦点を当て、行動の理由や目的を探るものです。
つまり、行動の原因や責任を、障害・本人・家族のせいにしません。
あくまで、環境との相互作用から問題行動は生じるのであり、その中から問題行動の解決を見出すという学問です。
これらのことから、障害児支援との親和性の高さが分かると思います。
誰にでも有効なABA~応用行動分析学~


その観点から考えると、応用行動分析は、発達障害児や自閉症の支援だけではなく、知的障害、ダウン症、その他の障害をもつ、全ての人に対して効果的です。
例をあげてみましょう。
- 「他害」と言われるような、周囲に危害を加える行動をとる。
- 本人のこだわりから、周囲に迷惑をかけてまで行動を押し通そうとする。
- 過度な同一性保持や感覚遊びから、社会活動への参加が制限される。
上記のような子ども達は、ABA(応用行動分析)が効果的といえます。
さらに、行動の理由に焦点を当てるABAは「自分の子どもが、何故この行動を起こすのか。」の理解を促すため、保護者にもメリットがあります。
行動の理由が分かれば、子どもの気持ちを理解でき、イライラや育児の悩みの軽減につながるかもしれませんよね。
それでは、次にABAの具体的な支援の方法を説明します。
ABA(応用行動分析)で支援しよう➀~まずは、分析から~
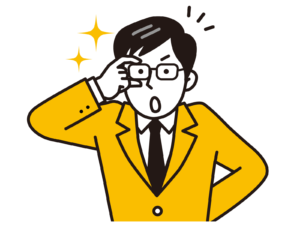
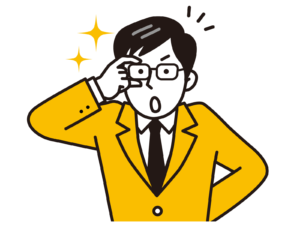
ABA(応用行動分析)で具体的に支援する前に、「問題行動」の分析が必要です。
以下、説明します。
➀ABC分析
行動前の状況と、行動の結果何を得たのか。
これらを明確にすることを「ABC分析」といいます。
- Antecedent(行動前の状況)
- Behavior(行動)
- Consequence(行動の結果)
例をあげます。
「対象」:5歳の女の子Aさん
「場所」:デパートのおもちゃ売り場
Aさんが、欲しいおもちゃを買ってもらえずに大声で暴言を吐いています。



おもちゃを買ってよう!! ママなんか大嫌い!! ママの馬鹿!! 消えちゃえばいいんだ!!



いい加減にしなさい!! もう…、買うから恥ずかしいこと言わないの。みんな見てるでしょ。
このときのAさんの行動をABC分析してみましょう。
※「Antecedent(行動前の状況)」
➔欲しいおもちゃを買ってもらえない
※「Behavior(行動)」
➔大声で泣く。暴言を吐く。
※「Consequence(行動の結果)」
➔おもちゃを買ってもらえた
上記のようなABC分析が成り立ちます。
暴言(問題行動)のみに目を向けるのではなく、ABCフレームに当てはめ、行動前・行動・行動の結果を客観的に分析しましょう。
➁行動の目的を発見する
問題行動の目的は、ほとんどが「欲求」によるものだと研究結果で明らかになっています。
Aさんの例だと「おもちゃが欲しい」という欲求ですね。
また、欲求の原因は4つに分けられます。
ABA(応用行動分析)で支援する際は、問題行動を引き起こす欲求がどれに当てはまるのかを分析することが大切です。
(1)要求の欲求
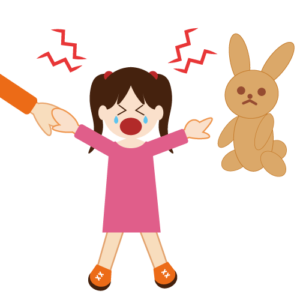
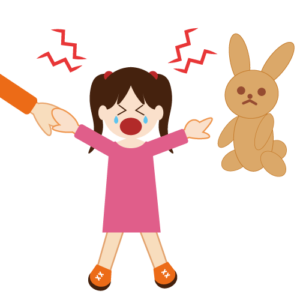
例えば、おもちゃ売り場で暴言を吐きました。
その結果、おもちゃを買ってもらえたので、「暴言を吐いたら、要求が通った。」という事実が強化子(行動の頻度を高める刺激)になってしまいます。
このことを学んだAさんは、繰り返し暴言(問題行動)を吐く可能性があるのです。
これは「ゲームをやりたい。」「○○を買ってほしい。」「○○の気持ちを押し通したい。」などの、本人の要求が問題行動に繋がっているケースの例になります。
(2)回避・逃避


回避・逃避の欲求は、発達障がいの子どもに多く見られます。
例として、学校に行きたくないBさんをあげましょう。
※「Antecedent(行動前の状況)」
➔学校に行きたくない。
※「Behavior(行動)」
➔親に頭が痛いと伝える。
※「Consequence(行動の結果)」
➔学校を休むことができた。(登校を回避できた)
「学校に行きたくない。頭が痛いと伝えたら行かなくてすんだ。」
このように、特定の行動で不快を回避できたという事実が強化子になります。
その結果、嫌なことを回避するために、今後も同じ行動を繰り返すようになるのです。
これが「回避」になります。
また、逃避は「予想していないタイミングでテストが行われる。嫌だから、退室する。」など、嫌悪事態を避けるために繰り返す問題行動のことをいいます。
(3)注目


例えば、
- 家具を壊したら家族に怒られた。
- 学校で悪ぶっていたら先生に注意された。
- 悪ふざけしていたら、クラスメイトが笑った
上記をABC分析のフレームに当てはめると、以下のようになります。
※「Antecedent(行動前の状況)」
➔注目されたい。(注目・注意喚起の欲求)
※「Behavior(行動)」
➔家具などを壊す。
※「Consequence(行動の結果)」
➔家族に怒られた。(注目を集めることができた。)
「周囲の目を向けさせたい。」、「注目してほしい。」など、注意喚起的な欲求が問題行動に繋がっているケースです。
(4)感覚


例えば、
- 自分の髪の毛を抜く。
- 繰り返し、反芻を行う。
- 急に離席してクルクル回る。
上記をABC分析のフレームにあてはめると、以下のようになります。
「朝の会の途中で髪の毛を抜いてしまう、Cさんの場合」
※「Antecedent(行動前の状況)」
➔朝の会終了までの見通しがもてずに不安である。
※「Behavior(行動)」
➔髪の毛を抜く。(感覚刺激/問題行動)
※「Consequence(行動の結果)」
➔髪の毛を抜くことで、不安を紛らわすことができた。
結果、Cさんは、髪の毛を抜くことで不安を紛らわすことができました。
しかし、この場合は、髪の毛を抜く(問題行動)ことの刺激自体が快になっていることが多くあります。
刺激が快になっている場合は、それが強化子となるため注意が必要です。
ABA(応用行動分析)で支援しよう➁~具体的な支援方法~
ABC分析で、行動により「何を得ているか。」「何がきっかけになっているか。」などが見えてきたら、支援を行いましょう。
支援方法には、「強化」「弱化」「消去」「先行条件操作」があります。
それぞれ、詳しく紹介します。
(1)強化


結果によって行動が増えることを「強化」といいます。
ABA(応用行動分析)では、子どもが良い行動をした際には褒めたり、褒美をあげたりすることで、良い行動を強化するのです。
これを、正の強化といいます。
分かりやすく、例をあげましょう。
トイレトレーニングに取り組んでいるDさん
➀おしっこがしたくなった
➁大便器でおしっこができた(行動)
③ご褒美の一口チョコが貰えた(正の強化)
➔ご褒美が貰えたことで正の強化が成り立ち、➁の行動が増える。
これを繰り返すことで、➁の行動を増やしていくのです。
きっと、一人でトイレができるようになるでしょう。
(2)弱化・消去
強化とは正反対の支援方法です。
あくまで子どもへの教育的指導方法の1つです。
子どもへの配慮を忘れてはなりません。
(3)先行条件操作


ABC分析の「Antecedent(行動前の状況)」に原因がある場合に用いられる支援方法です。
問題行動の原因となる時間や物を、事前に調節しておく方法になります。
再びAさんの例をあげます。
「対象」:5歳の女の子Aさん
「場所」:デパートのおもちゃ売り場
Aさんが、欲しいおもちゃを買ってもらえずに大声で暴言を吐いています。



おもちゃを買ってよう!! ママなんか大嫌い!! ママの馬鹿!! 消えちゃえばいいんだ!!



いい加減にしなさい!! もう…、買うから恥ずかしいこと言わないの。みんな見てるでしょ。
この場合、おもちゃ売り場での暴言を避けるために、「先行条件操作」を行います。
例えば、事前に「今日はおもちゃを1つ買うよ。」「今日は買わない。」などの約束をしておくのです。
または、「褒美のスタンプが5個貯まったら買おうね。」でもOKです。
これにより、問題行動を防ぐのです。
多少、専門性が求められる支援方法になります。
以上が、ABA(応用行動分析)の具体的な支援方法となります。
専門性が必要となる支援方法ですので、よく理解してから実践するようにしましょう。
保護者様へ~家庭でのABA(応用行動分析)について~


ABA(応用行動分析)は、特別支援学校や放課後等デイサービス、児童発達支援事業所など、専門性の高い支援員がいる現場で行われています。
近年では、家庭でも支援できるようにと、保護者向けの研修会が行われていたり、本や動画も出だされていて、誰でも実践できるような環境にあります。
ただ、気をつけて欲しいのは、家庭でABAを実践するのは保護者にとって負担になりやすいということです。
負担過多になり、親子共々ストレスを抱えてしまっては、本末転倒になります。
技術・労力・時間的な問題を和らげるためにも、なるべく専門施設の支援員に相談してから家庭で取り組むかを決めてください。
ABA(応用行動分析)のまとめ
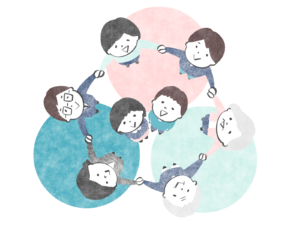
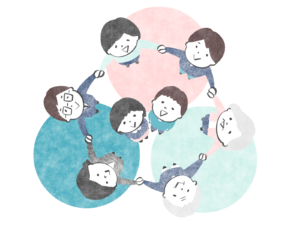
ABA(応用行動分析)の実践は、子どもの行動を理解するきっかけになります。
「障害や本人の特性から、問題行動が起きている。」などの大まかな理解ではなく、子ども一人ひとりに行動を起こす目的があると理解するからです。
「何故、この行動を起こすのか。」、「この行動の背景には何があるのか?」。
子どもの行動には、必ず原因があります。
最後に


今回はABA(応用行動分析)の概要や具体的な支援方法についてお話しました。
日々、子どもを支援していると、どうしても問題行動は起きます。
どんなに支援員が配慮していても起きてしまうのです。
そのとき、何が原因かを分析しましょう。
問題行動の目的が分かれば、本人はもちろん、家族の気持ちの安定にも繋げられます。
また、適切な支援により問題行動が減ることで、家族にかかる負担も少なくなります。
発達支援においてABA(応用行動分析)は、子どもだけではなく、家族の方への効果も期待できる支援方法なのです。
日々、子どもたちの成長のために何ができるか?
はぐちるランドは、より良い支援を提供していきたいと思います。
子ども達と家族のアスのために。
コノアス合同会社 代表 柏木でした。
はぐちるの森は、こどもたちの明日を考えるブログ
子どもたちの発達をゆっくり支援していく施設「はぐちるランド」を運営しています。
はぐちるランドは、子供たち一人ひとりがこれからの未来を楽しくのびのびと生活できるよう援助、療育を行う施設です。
また、児童発達支援施設の開設・運営をトータルサポート
子どもたちの未来のために、一緒に支援する場所を作っていきたい方の応援をしております。










コメント